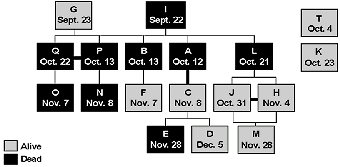
拙稿第3回で、ウルグァイで初の腎症候性出血熱(HFRS)が発生したかもしれないということを書きました。 私はウイルス病のことは全く素人ですが、その後一寸勉強してこの例はHFRSをおこすウイルスとは違うタイプのハンタウイルスによっておこる肺症候群(hantavirus pulmonary syndrome, HPS)らしいことがわかりました。 JICAチームリーダー井上氏がインターネットで得た次の二つの情報(95/5/15版)によるものです。 インターネットのメーリングリスト promed-aheadのダイジェスト版で得ることができるそうです。
HFRSは旧大陸ハンタウイルス(old world hantaviruses)感染によるもので、ユーラシア大陸では少なくとも40年以上にわたって毎年10万件以上発生しています。 ところが、1993年春にアメリカ南西部で肺に重篤な症状を来して高死亡率を示す肺症候群HPSが報告され、その流行はdeer mouse (Peromyscus maniculatus) によって媒介される新しい型のウイルス(a new world hantavirus), Sin Nombre Virus (SHV)と関連していることが分かりました。 スペイン語でsinは英語のwithout, nombreはnameのことを意味します。 その後、このネズミの生息地以外の所でHPS関連の3つの病原ウイルス新型 ---コットンラット媒介のBlack Greek Canalウイルス、ライスラットで同定されたBayouウイルス、白アシハツカネズミP. leucopusから分離されたNew Yorkウイルス--- が発見されました。 これらのウイルスはカリフォルニアでは検出されていません。 しかし、次の二つの新しいハンタウイルス ---El Moro Canyon Virus (EMCV)とIsla Vista Virus (ISLA)--- は最近カリフォルニア州で検出されました。 遺伝的検査の結果、EMCVはカヤネズミ、ISLAはハタネズミ(Microtus californicus) が保有者であることが分かりました。 ただし、これらのウイルスのヒトへの感染例はまだ報告されていません。
カリフォルニア州衛生局は同州における哺乳動物の横断的血清抗体検査を行いました。 すなわち、合計4626頭の哺乳動物についてSNV抗体の有無を血清学的に調べたところ、非齧歯類はすべてマイナスでした。 野生齧歯類のうち抗体分布はハタネズミ属やカヤネズミ属で多く、M. sp.で17.2% (5頭/29頭)、M. californicusで22.7% (5/22) 、カヤネズミで14.8% (16/108) でしたが、これらはヒトに感染しないISLAやEMCVに起因するものでした。
白アシハツカネズミの類のdeer mouse, Permyscus sp. は9.7% (236/2430)の保有率でとくにP. maniculatus で11.8% (226/1921) でSNV陽性が多く検出されました。 南カリフォルニア沿岸のサンタ・クルス島のこの種では35頭のうち実に71.4%の個体がSNV抗体を保有していました。 そして、ヒトのHPS発症地域の近辺で捕獲されたdeer mouseの抗体保持状況(164頭中の26.8%)は他の地域からのそのネズミの状況より有意に高率でした。 また、抗体分布は海抜高度が上るにつれて多くなり、ネバダ山脈におけるHPSの場所的分布とよく相関していました。 deer mouseの保存血清の抗体調査からSNVは20年前からカリフォルニア州の一部に存在して長く留まっていることもわかりました。
このように、肺に異常をきたすHPSはこのネズミに長年にわたって保持されているSNVに起因しているものと考えられます。 日本の厚生省では、動物からヒトにうつる可能性のある人獣共通感染症のうち、サルが媒介するエボラ出血熱などウイルス性出血熱、キツネの寄生虫によるエキノコックス症などの他、ネズミが媒介するハンタウイルス肺症候群の国内侵入を防ぐため、厚相の諮問機関である公衆衛生審議会で昨年7月から従来の感染症対策の抜本的見直しを進めています。
ハンタウイルスには多くのタイプがありますが殆んどはネズミ類の排泄物のエアロゾルを通して伝達すると考えられています。 しかし、1995年、アルゼンチン南部におけるHPS 20例は疫学的にヒトからヒトへ感染する可能性があることを示唆しています。 添付してある図を参考にしながら説明します。
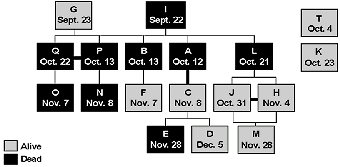
1996年9月22日、アルゼンチン南部の小都市エル・ボルソン (人口15,000、海抜350m) に住む41才の男性 (指標患者I) がHPS様症状を呈し、集中的な治療を受けるために150Km北のバリローチェに移されました。 そこで臨床症状とELISAによってSNVによる感染症と判定されました。 続いて70才になる彼の母 (患者B) と彼の医者の一人 (患者A) がHPSにかかりました。 その医者の妻は同じく医者でしたが彼女の夫の発症後27日でHPS (患者C) になりました。 彼女は治療のためにブエノス・アイレスの病院に行き、そこで女性の医者 (患者D) と一時間症状について話しました。 この医者は何層ものガーゼの下でCの腕から静脈穿刺をしましたがとくに血液にはふれていませんでした。 他にDがCに接したのは、2日後に他の患者を診るために病院の集中治療室に一寸の間行った時だけです。 DはCに会った24日後にHPSになりました。 Dはブエノス・アイレスの外には出ませんでしたし、発病前2ヶ月はネズミと全く接触していません。 ブエノス・アイレスに住む40才の女性の医者 (患者E) は患者Cが入院してから17日目にHPSになりました。 この方は患者AとC (夫婦) の友達で患者Aが死亡した後エル・ボルソンに3日間滞在していました。 彼女は、しばしば病院で患者Cを訪ねていますが直接HPS患者の臨床処置はしていません。 5番目の医者 (患者F) は数人のHPS患者と密接に接していました。 彼は患者Bの咽喉に管を入れたり、患者Iも診ています。 彼は、また、同僚 (患者A)とも接触しており、患者Iの妹 (患者H)、そのいとこ (患者J) と友達 (患者K) とも話をしたことがあります。 患者Bの葬式の時に患者Iのメイドの患者Lは既にHPSの症状を呈していました。 彼女は患者H,J (夫婦) とその娘さん (患者M) と車に同乗してブエノス・アイレスに帰りました。 3人はその後、11, 15および29日にそれぞれ発症しました。 3週後に車を調べましたがネズミ類が生息していたという証拠はみつかりませんでした。 患者HとJは数晩患者Iの家に滞在しましたものの患者Mは患者Bの葬式が行われたエル・ボルソンから250マイルも離れたハコバッティーにしか行っていません。
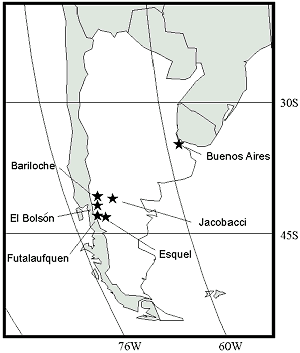
HPSの第2のグループはアルゼンチンの有名な観光地バリローチェで起こっています。 エル・ブロンソンの患者の多くが運ばれた病院に見舞いに行った人とその病院で働いていた人の計4人 -- 病院の夜間受付係 (患者N)、HPSと関係のない入院患者を見舞いにきた40才の女性 (患者O)、27才の男性 (患者P) とその妻 (患者Q) -- です。 PとQは9月20日(彼らの27週齢の胎児が出生した日)からその赤ちゃんが死亡した日、10月27日の間、何回も病院に行きNと親しくなりました。 3人はマテ茶を一本の金属製のストローでまわし飲みしたり、また、PはときどきNのキャンプ用ベットを借りて休んでいました。
この期間におけるエル・ボルソンの残りの3人のHPS患者は47才の男性 (患者G)、29才の男性 (患者R) それに14才の男の子 (患者T) です。GとTとは友達であったかあるいは1人以上のHPS患者と知り合いであったかどちらかですが、彼らが発症する前6週間はHPS患者と接したことはありませんでした。
以上のうち患者Cから彼女の医者 (患者D) への伝達ルートはヒト−ヒト感染の可能性をとくに示唆しています。 また、過去20年間にわたるネズミ捕獲データで、1996年春の本症流行地の生息密度が平均より有意に低いこともヒト−ヒト伝達の仮説を支持するものです。 もちろん、この仮説をはっきりさせるためにはもっと詳細な疫学的ならびに実験室的研究が必要ですが、ネズミによるzoonosisの他にもヒト−ヒトのルールを考慮する必要があります。
私がここ獣医研究所DILAVEに来た時に構内に非常に多くのネズミ類の穴とケモノ道があることに気がつきました。 周囲は草原であることから、前々から興味をもっていたアペリアというモルモットに似た動物ではないかと思い、捕獲しようといろいろな方法を試みたところとれたのは野生のドブネズミばかりでした。 そこで、実験動物棟の周辺だけでも除去しようと思っていたところ、「初のハンタウイルス感染か?」とウ国のマスコミがネズミ類との関係を取上げたこともあって、反応の早い所長のDr.Bは早速ネズミ退治の専門家に事前調査を依頼し駆除対策会議を開きました。 そして、現在、その対策に基づいてネズミ退治を実施しています。 ハンタウイルス騒動で、実験動物棟周囲だけでなくDILAVE全構内のネズミはぐっと少なくなることでしょう。